著者:冨田和成(とみた・かずまさ)さん
・株式会社ZUU 代表取締役
・2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。2013 年3 月に野村證券を退職。同年4 月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。
・2016-2017 年度監査法人トーマツ主催「日本テクノロジー Fast 50」にて2年連続上位受賞。
・2018年6月、設立約5年で東京証券取引所マザーズ市場に上場。
 悩み人
悩み人計画を立ててもいつになってもゴールまでたどりつかない・・・
 もちパン
もちパンそんなときは冨田和成さん著書の『鬼速PDCA』を読むのをおすすめするよ! 身近なことで出来る事が沢山書かれているよ。読んで実践してみてね!
本書でこんなことが分かります!
・PDCAのフレームワークは誰でも実践できる!
・失敗は仮説の精度を高める!だから楽しもう。
記事の信頼性
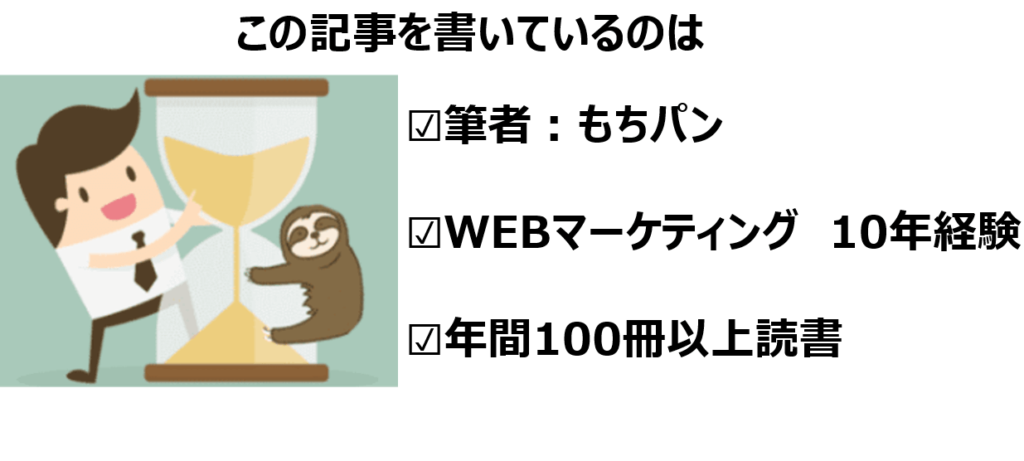
【結論】鬼速でPDCAをぶん回して、プロセスを楽しみながらゴールまでたどり着こう!
私なりに、『鬼速PDCA』について、ギュッと凝縮して解説しました!
それでは、いきましょう!
図解バージョン
鬼速PDCAとは?
通常のPDCAは、みなさんご存知かと思います。
• 計画(Plan)
• 実行(Do)
• 検証(Check)
• 改善(Action)
しかし、鬼速PDCAでは「Aciton」ではなく「Adjust」を用いています。
• 計画(Plan)
• 実行(Do)
• 検証(Check)
• 調整(Adjust)
通常は改善(Action)を用いますが、鬼速PDCAが調整(Adjust)を使うのには理由があります。
PDCAの特性として、計画が止まってしまうことを防ぐ効果があります。
1. 悪い面の改善ではなく良い面の伸長という意味
2. ActionとDoが混同しがちであるという観点があります
鬼速PDCAを効果的に回すには計画(PLAN)が最も大切
本書では、特に計画の大切さが強調されています。
筆者は、失敗の原因の半分は、計画立てが甘いこと、と述べています。
計画がなければ、行動も適当になり、調整するときも計画を基にすることができず、効率・効果が悪くなるのです。
計画をしっかり立てることで具体的に把握しやすい行動を決めることができます。
行動に移せない計画とは、以下のケースに分けられます。
・計画自体が失敗
・計画がない
・計画が無茶
・計画が粗い
それでは、どのように計画を作れば良いのでしょうか。
良い計画(PLAN)を作るポイントは?
本書を読んで良い計画を作るポイントをまとめました。
• 計画を立てる前にゴールを決める
• なぜそのゴールを目指すのか?を明確にする
• ゴールはできるだけ具体的に書く
(ゴールまでの計画を立てたら質問をして計画を検証する)
• ゴールまでの計画を仮説を立て「もっと効率的な⽅法はないのか?」「⾒えていない課題が潜んでいるのでは?」を問う
計画を立てたらその計画について検証を重ねて、良い計画にしていきましょう。
魔法の言葉「他にできることがあるとしたら何なのか?」
著者の会社では、部下から相談を持ち込まれたときに上司がよく言うフレーズとして、
「他にできることがあるとしたら何なのか?」と尋ねるといいます。
こうすることによって、部下に考えさせることができるそうです。
与えられた答えというのは、自分で思考をしていないので、思考プロセスを成長させることができないからです。
「他にできることがあるとしたら何なのか?」というフレーズは覚えておきましょう。
鬼速PDCAを実行(DO)するために大切なことは?
計画をしても実行することが出来なくて挫折していく人が多いでしょう。
それは本書の中では下記のように表現されています。
ビジネス書からたくさんの刺激を受けて、「やっぱり⾃分ってこのへんが課題なんだよな」とせっかく気づいても、それを具体的な解決案に落とし込まないから9割の⼈は読んで終わり
引用:鬼速PDCAより
つまり具体的な解決案に落とし込めば、読んで終わりにならないわけです。
また、本書の中では、計画段階で具体的に書くことにより実行フェーズに落とし込むことができるとも書かれています。
抽象的なアクションを「毎⽇、朝6時に起きて5キロ⾛る」「今⽇、⼣⾷後の2時間を使ってネットで検索する」といった具体的なタスクとしてスケジュールを押さえてしまえば、もはややらざるを得ない状況に⾃分を追い込むことができる。加えて、やることが具体的だと、取り組む意欲が増すという⼤きな効果もある。
引用:鬼速PDCAより
やること全てに意味を持たせる
実⾏するときは自信満々で実行することが大切であるとも言われています。
計画したことが失敗することは当たり前であって、むしろ仮説の精度を高めることになります。
部下が失敗した際は、「仮説の精度が高まったね」と声を掛けと本人のやる気につながっていくことになります。
変化の激しい時代で、失敗を恐れずに行動していきましょう。
意識的に行動(DO)の数を減らす
計画を因数分解して具体的な行動を明確にすることができれば、すぐに行動に移すことができます。
しかし、計画を立てていくと行動(DO)の数が自然と増えていきます。
その場合、捨てられる行動(DO)を見つけて、本当に必要なことに集中しましょう。
割合にすると7割の行動は捨ててしまい、3割に絞り込むと良いと本書では言っています。
また、非効率なルーチンも見直しをすることが大切です。
実行したら検証(CHECK)をする
1日の仕事内容を振り返ると、その多くをPDCAのうち「D(実行)」が占めていると思います。
実行がうまくいかないとPDCAはストップしかねません。
そうならないためにも、実行を妨げる「障害」や「無駄」を一刻も早く取り除く必要があります。
そこで必要になるのが、「検証(CHECK)」の頻度です。
日々行っているタスクの進捗検証は毎日すべきですし、行動目標も数値化し、3日に1回は検証すべきです。
また、検証の失敗パターンを覚えておきましょう。
失敗パターン1
せっかく計画を立て実行に移しているのに検証をしない
失敗パターン2
ろくに計画も立ててないのに形式的に移しているのに検証をしない
検証する際に大切なことは、 客観的な視点で分析をすることです。
• 客観的視点の分析
できなかった要因については、どうやったらできるようになるか?できた要因については、どうやったらさらに成果を出せるか?を考えます。
自分の計画や行動に対して「頑張った自分」ではなく、結果に対して客観的に見ることが大切です。
主観的な判断をしてしまうと、改善点を見落とすことがよくあります。
トヨタ式の改善でも有名な話ですが、本書でも分析の基本は「なぜ」の繰り返しであると言われています。
トヨタ式では、5WHYを行い、根本原因を突き止めることができます。
鬼速PDCAの独特な点である調整(ADJUST)は大きく4つある?
調整フェーズは最後に来るというイメージではなく、計画フェーズや実行フェーズだけでなく、検証フェーズでも細かく調整をするのが大切だと言われています。
• ゴールレベルの調整が必要なもの
• 計画の大幅な見直しレベルの調整
• 解決策や行動レベルの調整
• 調整の必要がないもの
調整のレベルによって対応がことなりますが、うまくいったことやうまくいかなかったことについて考え、「できなかったこと」を改善するだけでなく、「できたこと」の伸長案も考えて、次のサイクルでやるべきことを調整するのが、スピード感のある前進を可能にします。
鬼速PDCAを習慣化するための仕組み・・・図解版のみ
鬼速PDCAを習慣化するためには、心理的ハードルをいかに下げるかが重要です。
あまり難しく考えず、計画を因数分解していって簡単に行動できるレベルまで落とし込みます。
小さなことから始めることによって、プロセスを楽しむことが可能になります。
日常のささいなことが、大きなゴールに向かっていることを考えると、とてもワクワクすると思います。
小さなPDCAを同時に複数回すことにより、より鬼速PDCAの効果を高めることができるそうです。
ぜひ、あなたも習慣化するために工夫をしてみてください。
まとめ
24時間、皆平等に与えられたの中で、より効率的かつ効果的に仕事を進められるようになりました。計画を立てる段階から、甘すぎず、時間を掛け過ぎず、より自分自身が納得した上でPDCAサイクルのプロセスを回すことができます。失敗したときは、「仮説の精度が高められた」と思うようにすれば、楽しく実行できます。心理的な効果も継続していく上ではとても大きいと思います。ぜひ、本書を手に取って読んでみてください。
最近話題な本、数値化の鬼と比較して読んでみると面白いですよ!

図解バージョン
【著作権者(著者、訳者、出版社)のみなさま】 当ブログでは書籍で得た知識を元に制作しております。あくまでも、書籍の内容解説をするにとどめ、原著作物の表現に対する複製・翻案とはならないよう構成し、まず何より著者の方々、出版・報道に携わる方々への感謝と敬意を込めた運営を心懸けております。 しかしながら、もし行き届かない点があり、記事、動画の削除などご希望される著作権者の方は、迅速に対応させていただきますので、お手数お掛けしまして恐れ入りますが、問い合わせフォームからご連絡をよろしくお願い致します。









