 悩み人
悩み人先生や親から「勉強しなさい!」てよく言われるんだけど、学ぶことは本当に必要なのかな・・・?
 もちパン
もちパンそんなときは、「学問のすすめ」の本を読むことをおすすめするよ!
今回、この記事を書くにあたり、中央大学 文学部卒の友人に監修をしてもらいました!
本記事では、こんなことが分かります!
福沢諭吉が国民に伝えたかった「学問」の意味
150年前に出版されてから現代まで語り継がれている理由
記事の信頼性
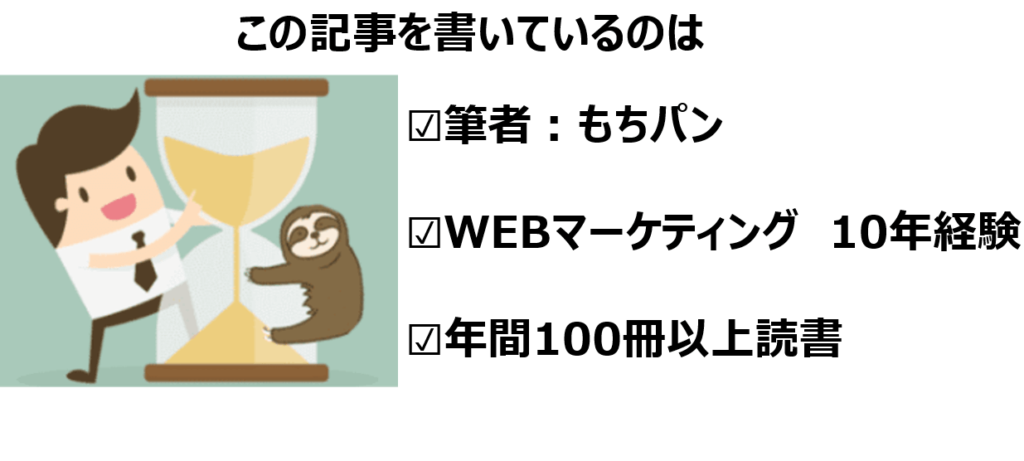
誰もが一度は耳にしたことがある「学問のすすめ」ですが、17編構成されています。
一言にまとめて解説してしまうと非常にもったいないのですが、結論を先にお伝えさせていただくと・・・
【結論】福沢諭吉が国民に伝えたかった学問とは、社会の役に立つ実学のためである。
現代語訳 学問のすすめ (ちくま新書)通勤や家事の時でも聞き流せる様に動画を制作しました!
前編1編から9編まではこちら
後編10編から17編はこちら
それでは、早速、解説をさせていただきます!
福沢諭吉の「学問のすすめ」とは?
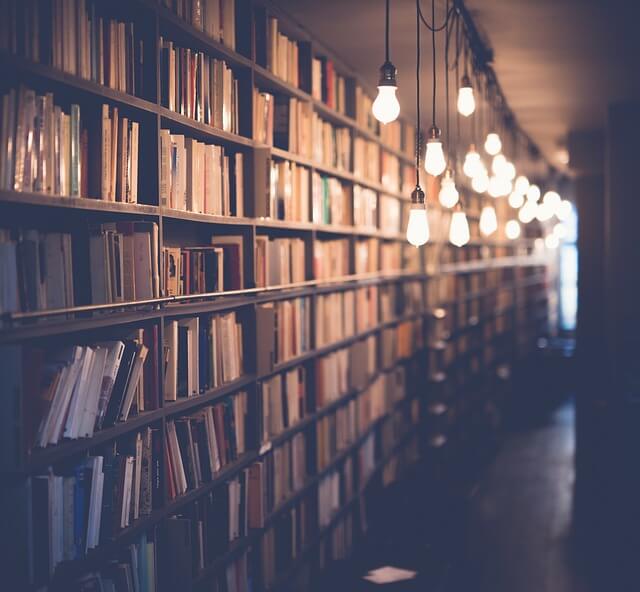
『学問のすすめ』は今から約150年前に出版されました。当時の日本人のほとんどは、中世以降の封建社会や儒教しか知らないまま、明治維新迎えます。
その国民に対して、日本が近代国家への道を歩み出したこと、民主主義国家の主権者となるべき、自覚ある市民に意識改革する啓蒙として、本書は書かれました。
近代日本の啓発書で最も著名で、最も売れた書籍です。当時、最終的には340万部売れたとされ、当時の日本の人口が3000万人程であったことから、全国民の10人に1人が買った計算になります。
明治維新の動乱を経て、新しく開けた新時代への希望と、国家の独立と発展を担う責任を自覚する明治初期の知識人の気概に満ち、当時の日本国民に広く受容されました。
本書の各編をご説明させていただきます。
第1編 学問には目的がある
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」
賢い人と愚かな人との違いは、学ぶか学ばないかによってできるもの。
役に立つ学問とは、普段の生活に役立つ実学である。学問を学んで、個人的に独立し、国家も独立することができる。
政府の官僚を軽んじないのは、身分が尊いからではなく、国民のために尊い国の法律を扱っているから。個人でなく、国の法律が尊いのである。
私がすすめる学問は、国の平和と安定を守ることを目的としている。
第2編 人間の権利とは何か
本を読むことだけが学問ではない。文字は学問をするための道具にすぎない。
政府と人民は対等である。封建時代の悪い社会的慣習というものは、人間が平等の人権を持っていることを認識せずに、社会的な貧富、強弱を盾にとって、強い政府が弱い人民の権利を妨害してきたことにある。
また、国民の無知が原因で、自ら招いたこととも言える。だから、人民が暴力的な政府を避けたいならば、今すぐ学問に志して、自分の才能や人間性を高め、政府と同等の地位にのぼるようにしなければいけない。これが、私がすすめる学問の目的である。
第3編 愛国心のあり方
第二編で政府と人民の関係を話したが、国と国の関係も論じる。
今、アメリカ、ヨーロッパの諸国はアジアやアフリカに対して無理を与えている。
個人が努力により変わるように、国民も変わることで国を豊かにし、西洋人に対等に渡り合える。
それには国中の人民に独立の気概が必要である。国民を束縛して政府が苦労して政治をすすめるよりも、国民を解放し、苦楽を共にした方が良い。
第4編 国民の気風が国を作る
一国全体を整備し、充実させていくのは、国民と政府が両立してはじめて成功する。国民は政府の働きに任せて放っておいてはならない。
しかし日本の人民は、長い歴史の中で専制政治に苦しめられ、心に思うことを表現することができない性格である。
これでは国を思う余裕ができない。日本には政府ができたが、いまだ国民がいない、と言える。
我々はまずしっかりと自分達の立場に立ち、学術を教え、経済活動に従事し、法律を論じ、本を書き、新聞を出すなどして、国民の分を超えないことであれば遠慮なく行うべき。
国民は政府を恐れてはいけない。政府を疑うのではなく親しんでいかなければならない。
第5編 国をリードする人材とは
明治政府は学校を建て、工業を興し、陸海軍の制度を一新し、文明の形をほぼ備えた。
しかし国民はいまだに外国を恐れ、自分たちの独立を強固なものとして海外と競い合おうとしない。
原因は、日本が非常に長い間、全国の権力を政府が一手に握って、人民がただ政府の命じることを聞くことに慣れているからだ。国民が国を思う機会を持たない気風が育ってしまった。
西洋諸国の歴史を考える。蒸気機関はワットの発明。鉄道はスチーブンソン、経済の法則はアダムスミスであり、彼らは国の大臣ではなく下層の労働者でもない。
まさに国民の中くらいに位置して、知力で世の中を指揮してきた人たちである。文明を行うのは民間の人民であり、それを保護するのが政府である。
第6編 文明社会と法の精神
国民は一人で二人分の役割を務めている。1.自分の代理として政府を立てて、国内の悪人を取り締まり善人を保護する。2.政府との約束を固く守って法に従い保護を受ける。だから決して法に背いてはならない。
忠臣蔵の敵討ちも暗殺も私裁であり良くない。
政府が法を作るときは、なるべく簡単にするのが良い。法が定まった以上は、厳格に守らなければならない。法が不当だと思えば、国民は論じて訴えるべきであり、勝手に判断して行動すべきでない。
第7編 国民2つの役目
1.政府の元に立つ1人の民、つまり客の立場。
2.国という名の会社を作り、会社の方を決めて実施する、つまり主人の立場。
無駄な税金の使われ方をしたと思われるときだけ批判するのではなく、普段から良く気をつけて政府の処置を見る、遠慮なく穏やかに議論すべき。
税金は気持ちよく払い、政府の庇護を買うべき。
第8編 男女間の不条理、親子間の不条理
不条理な男女間について、世の中では、力ずくで人の物を奪い辱めるものがあれば罪人になるのに、家の中で同じことをしても問題にならなかったのはなぜか。
女はなぜ嫁いで夫に従わなければならないのか。妾制度も同様。「男妾」がないのはなぜか。男女の強弱がそうさせるのであって、自然なことではない。男尊女卑は不合理である。
不条理な親子間について、子は親を苦しめているから恩を返さないとならない=孝行しなければいけないという。
しかし、子を産んで養うのは人類だけでなく他の生物も行っている。理屈に合わない姑、親の言うことを聞くというのは悪い習慣である。
第9編 よりレベルの高い学問
人間の心身の働きは2種類に分けて区別できる。
1.一個人としての働き。2.社会的交わりの中での社会人としての働き。
1.だけだと、ただ生まれて死ぬだけ。
2.世の中、後世、子孫のために働く。文明は、世界中の過去の人々が一体となり、今の世界の人々(我々)に譲り渡してくれた遺産である。我々も発明、日々改良し、世の中や未来の人に遺さなければならない。
封建制度のときには機会が恵まれなかったが、戊辰戦争後の変動は文明に促された人々の変動であり、今の学生はチャンスに出会っているのだから、世の中のために努力しないわけにはいかない。
第10編 学問にかかる期待
初歩の学問で満足し、勉強を個人の生計を立てるためだけに利用するのではなく、学問をより進めて国家のために行い、外国人と知恵で戦い、日本を発展させてほしい。
第11編 美しいタテマエに潜む害悪
一部の目上の人だけが考えて世の中の多くの愚かな人を救うという名分は、善意から生まれた。親子関係なら理にかなうが、政府と人民は他人なのでこれに当てはまらない。
名分でなく職分を代入するといい。職分とは、自分の立場による責任である。
第12編 品格を高める
日本には演説、スピーチという文化はなかったが、これはとてもよい手段である。文章よりも口頭の方が理解しやすく人の心を動かすものがある。1人の人間が考えていることをより多くの人にスムーズに伝える方法を考えるのは大切だ。
読書だけではいけない、実際に活かすことが学問で重要だ。観察、推理、読書で知見を持ち、議論で知見を交換、本を書き演説し知見を広める手段とする。
人間の見識、品格を高めるには、物事のようすを比較して、上を目指し、決して自己満足しないようにすることである。
学校のレベルは風紀でなく、学問の質で決まる。
かつての大国インド、トルコは、今や西洋の属国のような扱いだ。これらの国は自国に満足して他国との比較を部分的にしかしないで、判断を見誤ったからだ。
第13編 怨望は最大の悪徳
怨望は、言論、行動と自由の制限から生まれた。貧乏や地位の低さでなく、人間本来の自然の動きを邪魔して、いいことも悪いことも運任せの世の中になると流行する。だから言論の自由は妨げてはならない。
第14編 人生設計の技術
人間は自分で思っているよりも愚かなことをするし、ことの難易度と時間の見積りをすることが下手である。
そこで、事業と成否、損得について、ときどき自分の心の中でプラスマイナスの差引計算、つまり棚卸しをするとよい。
生まれて今まで自分は何事を成したか、今は何事を成しているか、今後は何事をなすべきか、と、自身の点検をする。
第15編 判断力の鍛え方
信じることには偽りが多く、疑うことには真理が多い。西洋が今日の文明に達した原因も、すべて既存で信じられていることを疑うという一点から出ている。
例、ガリレオの地動説、ニュートンの重力、クラークソンの反奴隷運動、ルターの宗教改革。アジア人が迷信を信じたり、聖人賢者の言葉を聞いて一時的に共感しずっと縛られているのとは比べ物にならない。
ただし、物事を疑うには取捨選択の判断力が必要で、それには学問が必要だ。
当然ながら、西洋文明を盲信するのは良くない。東西の時物を良く比較し、信ずべきことを信じ、疑うべきことを疑う。そうした力は学問によって養われる。
第16編 正しい実行力をつける
人のものを見て自分もそれを欲しがる、など物に支配されてはいけない。独立ができなくなる。議論と実行は異なる。
議論は内側に存在し自由で制限のないもの。実行には制限がある。両者は齟齬しないよう、バランス良くなければならない。
他人の仕事を見て物足りないと感じたら、試しに自分でやってみる。他人が書いた本を批判したかったら、自分でも本を書く。思っていることと行動のバランスを取る。
第17編 人望と人付き合い
人望は実際の力量や財産が多くあるからといって得られるものでない。その人の活発な知性の働きと正直な心という徳をもって、次第に獲得していくもの。
栄誉や人望は、努力して求めるべきものである。ただしバランスを取ることが重要だ。
自分の力を発揮して世の中のためになるようにするには、以下のことが必要。
1.言葉を勉強し、弁舌を上達させる。
2.表情、見た目の印象で人に嫌な感じを与えない。
3.旧友だけでなく、新しい友人を求めるようにする。さまざまな方面に関心を持ち、多方面で人と接する。
まとめ
福澤諭吉の言う「学問」とは、社会の役に立つ実学のことです。学問をすれば自分の意識がはっきりし、経済がうまく回り、幸せな生き方ができる、国家社会の役に立てると福澤は言います。お金儲けと、社会のための事業は両極だと考えがちですが、福澤は同じ方向にあると言っています。
国家政府は国民一人ひとりのために安全保障をして守るべきであると述べる一方、国民は気持ちよく税金を払い、少しのお金で安全を買えと言います。普段から政府の在り方や世のあり方について議論するためにも学問が必要です。
当時は当たり前だった考え方(忠臣蔵の敵討ち、女性の義務)に対してビシッと批判しつつもユーモアな例え話で語りかけるため、読んでいる人の心にスッと入っていきます。また西洋のことをなんでもありがたがるのではなく、学問することで自身の比較判断力を養い、考えを深めて世の中に発信する大切さを説いています。
前近代(江戸時代)までの生き方で凝り固まった考えの日本人に、「国民」としての気概の持ち方の方法性を示した福沢諭吉の『学問のすすめ』。福澤は慶應義塾をひとつのビジネスモデルとして確立するなど、経済方面でも活躍をしました。時間の見積り、棚卸しや、正しい自己アピールの方法など、具体的なアドバイスも盛り込まれており、実学としての学問をわかりやすく伝えているため、現代の私たちが読んでもとても興味深く読める本です。150年語り継がれる理由はこのようなところに魅力があるかもしれません。
【著作権者(著者、訳者、出版社)のみなさま】 当ブログでは書籍で得た知識を元に制作しております。あくまでも、書籍の内容解説をするにとどめ、原著作物の表現に対する複製・翻案とはならないよう構成し、まず何より著者の方々、出版・報道に携わる方々への感謝と敬意を込めた運営を心懸けております。 しかしながら、もし行き届かない点があり、記事、動画の削除などご希望される著作権者の方は、迅速に対応させていただきますので、お手数お掛けしまして恐れ入りますが、問い合わせフォームからご連絡をよろしくお願い致します。
新1万円札といえば、渋沢栄一です。
渋沢栄一が現代の私たちに伝えたかったことは?「論語と算盤」の要約・感想です。








