 もちパン
もちパン僕が読んだお金に関する本15冊から
特に印象に残った共通点を紹介したいと思います。
こんな人におすすめの記事です。
・とにかく時間をかけずにお金に関する情報を得たい
・お金について学びたい方
✓記事の信頼性
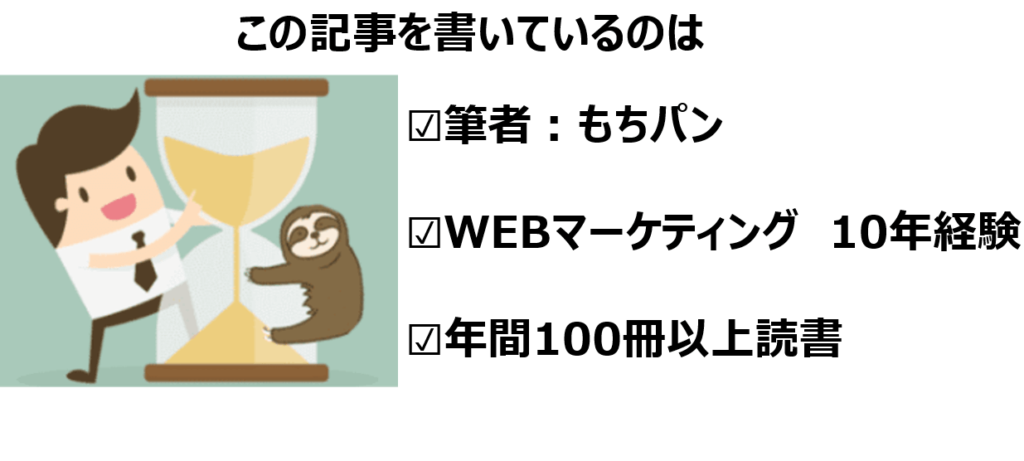
僕が読んだ本はこちらです。
もし、本に興味がある場合は、ぜひ、Amazonで検索してみてください。
1.お金の大学 両@リベ大学長
2.節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本 朝日新聞出版
3.図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください! 山崎 元 、 大橋 弘祐
4.バビロンの大富豪の教え ジョージ S クレイソン
5.世界一受けたいお金の授業 和仁 達也
6.お金が貯まらない人の悪い習慣39 田口 智隆
7.なぜ貯金好きはお金持ちになれないのか? 北川 邦弘
8.お金が貯まるのはどっち!? 菅井 敏之
9.お金で失敗しない人たちの賢い習慣と考え方 トーマス・ギロヴィッチ
10.狙うは地方1棟買い!目指せ年収10倍アップ!
11.金持ち父さん貧乏父さん ロバートキヨサキ
12.世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 高橋 ダン
13.12万人が学んだ 投資1年目の教科書 高橋 慶行
14.宇宙一ワクワクするお金の授業 大石 洋子
15.TIME SMART(タイム・スマート): お金と時間の科学 アシュリー・ウィランズ、 柴田 裕之
【共通点あり】僕がお金の本を15冊読んで分かったこと【要約】
お金は悪という考え方
人前でお金の話をしてはいけないと思っている方も多いのではないでしょうか?
戦時中の日本において物資が不足しており、当時の内閣は「国民精神総動員」という政策によって全国民に質素倹約を推奨しました。
「欲しがりません勝つまでは」の標語を掲げ、個人でお金を保有することを卑(いや)しいものとしたのです。
そのため、お金=卑しいと思っている方がいるのも事実です。
ただし、現代では、その考えはもう古くなりました。お金の話をして、より一層詳しくなりましょう。
教育は働くことを前提としている
日本国民の三大義務は、第一が働く義務、第二が納税の義務、そして第三が子供に教育を受けさせる義務です。
実際、僕たちが受けた教育というのは、一人一人の国民のために存在するのではなくて、元々が国を経営していくために作られたシステムでした。
労働者を養成する場所=学校
個人がしっかり社会に出て、働いて、税金を納めてくれれば国としては、それで良かったのです。
先生から経営者になる方法や、お金について詳しく教えてくれたことはありましたでしょうか?
僕は、教育免許を持っていますが、学習指導要領の中には存在していませんでした。
なぜなら、このような背景があるからです。
※ただ、2022年から高校で投資教育が実施され、金融リテラシーを高めるための授業が始まると言われています。
お金の本を15冊読んで学んだこと【ライフプランの重要性】
日本人は実は無計画
米国、中国と比較すると日本人は無計画ということが研究で分かっています。
日本は、米国、中国と比較すると貯金をしている傾向がありますが、貯金を何に使うか目的意識をはっきり持っていない人が7割という結果になっています。
日本人が、米国、中国、日本を比較した時に、どの国が無計画かを問われたときに、
『米国』と答える人が多いそうです。
フランクな印象から来るものだと思いますが、完全にステレオタイプです。
日本人は、あまり計画的ではないということを認識して、行動していきましょう。
貯金だけではお金持ちになれない
貯金だけでは、お金持ちになれない仕組みがあります。
それは、資本主義の中にあなた自身がいるからです。
雇われている側の人が一生懸命働いて、貯金をしたからと言ってもせいぜい知れているということです。
インフレリスクや働いても賃金が上がらないことを考えると、労働者側からお金を働かす側になれるかが鍵となります。
過去にトマピケティのr>gについて解説させていただきました。

最低でも10%を貯蓄にまわせ
バビロンの法則でも登場しますが、給料の10%の貯蓄をすることが大切です。
日本人の生涯年収は以前3億円と言われていましたが、実際に計算したところ中央値で約2億円が近いところです。
2億円の10%は、10分の1の2,000万円。
夫婦の場合、4,000万円程貯まる計算になります。
もし、貯蓄率を20%にできた場合、この倍を貯めることができます。
でも、これだけでなく、資産運用を行って3%程度で運用できれば、富裕層の1億円に近づきます。
準富裕層、富裕層を目指すのであれば、お金を貯めるだけでなく、中長期的な投資が必要になります。
お金の本を15冊読んで学んだこと【投資をするなら鉄則を守る】
投資は手数料の安いインデックスファンド一択
投資は、アクティブファンドとインデックスファンドが存在します。
インデックスファンドは、日経平均株価やTOPIXといった指数に連動するように設計された投資信託です。
一方、指数を上回る、または指数に捉われずにリターンの獲得を目指す投資信託がアクティブファンドです。
投資は、何と言っても大切なのが手数料を掛けない事です。
最終的に手数料が引かれて、思ったよりも利益が少なかった、とならないように、手数料は0.1%以下のものを選ぶようにしてください。
あの投資の神様のウォーレンバフェットは、「妻に残す遺産の9割をインデックスファンド(S&P500)で運用する」と公言しています。
どの個別株を買うよりも、インデックスファンド(S&P500)を中長期的な視点で購入した方が高い利益を得られると分かってしまったからです。
僕もインデックスファンドに投資をしています。
ドルコスト平均法
簡単に言えば、定期的に株を買うことです。
株価が悪いときに、多くの株を買って、株価が順調な時は、少しの株を買えば、より多くの株を手にすることができる手法です。
初心者の方はあまり深く考えず、定期的な積み立てぐらいに捉えておけば問題ありません。
銀行や証券会社の窓口にはいかない
先程、手数料の話をしましたが、銀行や証券会社の窓口へはいかないでください。
銀行や証券会社は、お客様から高い手数料を取ることで、会社を運営しており、社員に高い給料を払っているのです。
この世には、どちらかしかありません。
銀行員が喜んで、あなたが悲しむ。
あなたが喜んで、銀行員が悲しむ。
どちらを選択するかは、考えなくても分かりますよね。
今日から、窓口の人と会わない選択肢を持っていただき、もし、投資をする場合は、SBI証券か楽天証券の様なネット証券口座を開くようにしてください。
この2社は、手数料が安いファンドを保有しており、それぞれに強みがあります。
お金の本を15冊読んで学んだこと【資産を守る】
詐欺にあわない様に資産を守る
詐欺に合う人の特徴は、「私の場合は、大丈夫!」と自分を過信している人です。
しっかり、金融知識を身につけて、詐欺にあわない様に、知識武装すれば資産を守ることができます。
金融の本を読んだり、FPや簿記などの資格を取得したりして、本当に価値のある知識を身に付けましょう。
お金の学校の両学長は、簿記の資格取得をおすすめしています。
無駄遣いをしない家計管理
当たり前のことですが、悪い習慣を持っていると、あっという間にお金はなくなります。
ギャンブル、お酒、ついつい買ってしまうコンビニのコーヒーなど。
少しの積み重ねが、将来、大きな利益になることを忘れないでください。
無駄遣いをしないようにするために、家計管理をすることがとても大切です。
浪費、消費、投資の区別をつけて、管理していきましょう。
保険や携帯料金の見直し
人からの誘いに断れずに加入した生命保険、月1万円以上の電話料金などは、すぐに見直すことをおすすめします。
生命保険は最低限の掛け捨てにして、最悪な事態が起きた時に給料で賄えない分を、保険でカバーするようにしましょう。
銀行員、証券マンと同じく、保険屋にも合わない様にして、ネットで解決するようにしてください。
携帯は、格安SIMに替えて、月5,000円未満に出費を抑えれば、それだけで保険と合わせて月1万円~2万円程削減できるはずです。
稼ぐことは本当に大変ですが、出費を抑えることは誰でもできることです。
お金の本を15冊読んで学んだこと【最後に】
「この人は特別だから成功した。」という考えをもっていたら、いつになっても成功できません。
自分自身が成功していくために、今やるべきことを見極めて、行動していきましょう。
原理原則をしっかり理解して行動すれば、いつかは目的の場所にたどり着きます。
ぜひ、自信を持って今日から行動してみてください。
 もちパン
もちパン僕が、お金の本を15冊読んで気づいた共通点について、解説させていただきました。記事を読んでいただいた方が一人でも多くよりよい生活を送ってくれたら嬉しいです。








