著者:成田悠輔さんとは?
・中学高校時代は不登校気味。お父さんが失踪。
・東大に入って、首席で卒業。
・マサチューセッツ工科大学で博士号を取り、アメリカの超名門イェール大学の助教授をしています。
断言する。若者が選挙に行って「政治参加」したくらいでは日本は何も変わらない。これは冷笑ではない。もっと大事なことに目を向けようという呼びかけだ。何がもっと大事なのか? 選挙や政治、そして民主主義というゲームのルール自体をどう作り変えるか考えることだ。ゲームのルールを変えること、つまり革命であるーー。
 悩み人
悩み人大人は選挙に行けと言うけど、本当に行く意味あるのかな・・・
生活が良くなることもないし・・・
 もちパン
もちパンその気持ち凄くよくわかるよ!確かに、日本の若者はそう思っている人も多いね。これから僕たちがどう社会と向き合っていけばいいか一緒に考えてみよう。
こんな人におすすめの記事です!
・超天才 成田悠輔さんについてもっと知りたい人
・日本の未来が心配な人
✓記事の信頼性
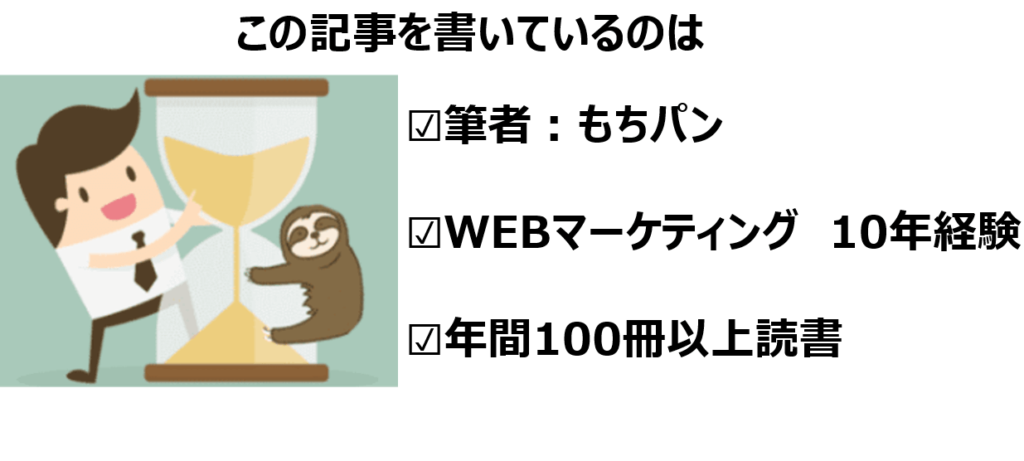
【結論】小さな革命を起こそう
成田悠輔さん著『22世紀の民主主義 選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる』について、私なりにかな~りかみ砕いて解説しました!
民主主義がぶっ壊れた理由

民主主義が古すぎてぶっ壊れてしまっている。
2千年以上前に民主主義が始まり、その当時は大発明だった。
でも、今の時代はそうでなくなってしまっている。

①現代は議論すべきテーマが多すぎる問題
②SNSに翻弄されすぎ問題
この2つが挙げられます。
現代は「議論すべきテーマが多すぎる」
テーマが膨大で、大雑把な括りをしたとしても経済、安全保障、エネルギー、社会保障、教育、デジタル化、コロナ、ダイバーシティなど、とんでもない量のテーマがあります。
そんな膨大な量のテーマがあるのに、数年に1回の一人一票の選挙で政策を決めるには無理があります。
基本的に、たった一つの政党を選ぶ仕組みになっていて、奇跡的に一致する政党なんてそうそう存在しない。
民主的に投票しようと言ってはいるが、選ぶに選べない状況になっているので、民主主義はぶっ壊れていると言えるわけです。
「SNSに翻弄されすぎな問題」
SNSが民主主義を急速にぶっ壊しているというのも、現代においては、SNSを活用すれば世論を操作することができます。
できもしないことを言い切ってしまえばいい。
例えば、ドナルド・トランプ元大統領は、分断を強調すると支持を得られていました。
菅さんの場合は、ワクチン接種を進めたり、携帯料金の引き下げ、不妊治療の保険適用、デジタル庁等々、一生懸命仕事をしていたのですが、あまり派手さがなく生きながらえることはできなかった。
SNSのパワーが強すぎるあまり、世論も政府もSNSに翻弄されがちで、その結果、政治家はパフォーマンス重視になっています。

将来を見据えた投資的判断ができてない状況だから、今の民主主義は完全にぶっ壊れている。
もはや若者が選挙に行き始めたことで何も変化がないことが成田悠輔さんの主張です。
そもそも、若者の人数が少なすぎる。
投票権を持っている人口は、30歳未満の若者の割合は、たった13%しかない。
そもそもボリュームがないので、投票率を改善したとしても意味がないと言っています。
60代の投票率は約60%、20代は30%と低いのですが、
仮に60代と同じ水準の60%に引き上げても超少数派からまぁまぁ少数派になるだけで、あまり意味がないということです。
若者ならココに投票すべきという政党がないことは、高齢者の方と投票する先が変わらないから意味がない。
例えば、若者が今の政治をぶっ壊したい!と思っていたとしたら、自民党以外の野党に投票するべきですが、
実際のデータではそうなっていないそうです。
自民党を支持する割合は、2~30代の若者と60代以上の高齢者を比べると、若者の方が高く、与党である自民党を支持してる。
今の政治でいい。今の政治家にプレッシャーをかける必要はない。という投票をしている。
だから、若者が投票に行こうが、日本の政治が変わることなんて無い。そう成田さんは断言されています。
この民主主義をどうにかしなければならない。
3つの対策 闘う、逃げる、革命

①闘う
今ある仕組みを改善するということです。
民主主義の仕組みに手を加えながらどうにか闘う道です。
具体的には、「若者よ選挙に行け」と呼びかけるだけでなく、「老人は引退しろ」と詰め寄るところまでやりきる。
若者の投票率を上げるだけでは変わらないなら、もはや高齢者の投票率を下げる。
策としては、投票する制限や政治家としての年齢制限を設定するなどです。
例えば、ブータンでは、65歳以上は立候補不可であり、ブラジルは70歳以下には投票を義務化していて71歳以上は投票をお任せしている。
ただ、年齢で、高齢者の方を排除してもあまり意味がない。
未来を見据えて判断してくれる高齢者の方もいるし、老害みたいな若者もいる。
シンガポールでは、年齢で区切るのではなくて、政治家がパフォーマンスに走らないように報酬でコントロールしている。
政治家が引退した後の未来の成果に対して、政治家の老後の年金を払う。
シンガポールの経済成長や未来の幸福度アップにつながったら、しっかり報酬を払うとしています。
民主主義の弱点である、世論に翻弄されて、目先のパフォーマンスに走りやすい仕組みを年齢制限・長期的な視点の報酬でどうにかしようという動きがある。
②逃げる
文字通り、民主主義の国家から逃げ出して、民主主義に縛られない場所に移り住む。
税金逃れのタックスヘブンに近いイメージです。(パナマケイマン諸島)
民主主義から逃げて自分たちだけの自由な国を作ってしまおう、といいます。
すでに始動していて、公海、誰のものでもない、公の海に独立都市を作ってしまおうと思っている人もいる。
Paypal創業者ピーターティールは、独立都市を作ろうとしている人の一人です。
そういえば、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、マークザッカーバーグも宇宙、海底、メタバースに夢中で民主主義から抜け出して、別の世界とルールを自分で作りたいと思っている人達です。
ただ、成田悠輔さんは、闘うことも逃げ出すことも根本の解決になっていない、といいます。
闘うと言っても、既存ルールに従ったら、支配している勢力が強いわけで勝てないし、
逃げ出すと言っても、お察しの通り、超富裕層だけに限定されていること。
そこで成田さんが提案するのが革命です。
③革命
データ分析とアルゴリズム研究が専門分野の成田さん的な視点で、民主主義の再発明を提案したいといいます。
ぶっこ壊れた民主主義を一回つぶして、新しい民主主義「無意識データ民主主義」に入れ替える。
無意識データ民主主義とは、国民の無意識のデータを収集して、それを政策に活かす。
数年に1回の投票ではなく、我々の日々の行動のデータが政策を決める。
例えば、Amazonのサイトで、日々、買い物をしていると勝手に商品をおすすめしてくれる。
データとアルゴリズムで政策を提案してもらうイメージです。
具体的に、国民のありとあらゆるデータを収集する。
インターネット上での動きとか発言、監視カメラがとらえている街中、会議室の中、自宅の中、表情、心拍数など、取れる限りのデータを収集し、膨大なデータからやるべき政策をする。
国民がなにを致命的な問題だと思っていて、どう対策したいと思っているのか、それを割り出す。
国民データ、成功事例、失敗事例などは、アルゴリズムが政策を人間に提案する。
その一方で政治家の人間は、政策を新たに考えるより、監視役になる。
アルゴリズムがあまりにもとんちんかんだった場合、拒否することだけが政治家の仕事になる。
これが成田さんが出した答えです。
選挙はアルゴリズムになり、政治家は猫になる。

成田さんは、このことを思考実験みたいなもので、異論反論があってもよいと言っています。
これは冷笑ではない。もっと大事なことに目を向けようという呼びかけだ。何がもっと大事なのか? 選挙や政治、そして民主主義というゲームのルール自体をどう作り変えるかを考える」ことだ。ルールを変えること。つまりちょっとした革命である。
まとめ
【結論】
今の日本の民主主義は終わっている。
若者が選挙に行ってどうにかなるレベルではなく、壊れてしまっている。
対策は3つ…
①闘争
②逃走
③革命を起こす
闘う、逃げ出すは根本的解決にならないから
ゼロから革命を起こすためには、無意識データ民主主義に入れ替えることが必要。
 もちパン
もちパン成田さんの新しい提案で今の民主主義の問題を再認識できたように思います。そもそも、今の民主主義は、データが全然足りていず、国民の声が反映されてないし、反映できる仕組みになっていない。
さらに、仮に我々の声を収集できたとしても対応ができない。
アルゴリズムのように24時間働けなければならないから数百人の政治家だけでは膨大な課題に対応ができない。この提案によって浮き出る民主主義の問題点について知っておくべきだと思いました。
【著作権者(著者、訳者、出版社)のみなさま】 当チャンネルでは書籍で得た知識を元に、ブログを制作しております。あくまでも、書籍の内容解説をするにとどめ、原著作物の表現に対する複製・翻案とはならないよう構成し、まず何より著者の方々、出版・報道に携わる方々への感謝と敬意を込めた運営を心懸けております。 しかしながら、もし行き届かない点があり、記事、動画の削除などご希望される著作権者の方は、迅速に対応させていただきますので、お手数お掛けしまして恐れ入りますが、問い合わせフォームからご連絡をよろしくお願い致します。









